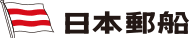空での取り組み
航空部門の安全への取り組み
日本貨物航空(株)では、2023年6月にIATA(International Air Transport Association:国際航空運送協会)が実施するIOSA(IATA Operation Safety Audit)を受験し、IOSA認証登録が更新されました。有効期間は2025年10月19日までとなります。
このAuditは航空会社の運航が安全に関する国際基準に基づき実施されていることを確認するもので、監査項目は1,000項目程度に及び、運航、整備のみならず、安全管理体制も確認される広範なものです。この監査項目は、毎年見直され、最新の国際基準が反映されていきます。監査員5名で5日間にわたる監査が実施され、2年毎に更新のための監査を受験し、合格する必要があります。次回の監査は2025年6月を予定しています。IOSA認証を維持するということは、国際的に高い水準で安全な運航を行っていることが認められたということになります。この水準を維持するため、毎年、社内監査を行い、IOSAの監査要求事項を満たしていることを継続的に確認しています。