日本郵船が脱炭素の公平・中立な国際ルールづくりに果たす役割
公開日:2025年10月31日
更新日:2026年02月06日

地球規模で深刻化する環境問題を背景に、GHG(温室効果ガス)の排出量削減は、海運業にとって急務といえる課題です。 脱炭素というグローバルに取り組むべき課題に効果的に取り組むためには、世界各国が公平かつ中立な国際ルールのもとで協調していくことが求められています。 国際海運ならではの“複雑”な事情と脱炭素に向けた日本郵船の取り組みをご紹介しましょう。
【おすすめの関連記事を読む】
海運業の脱炭素への道のりを複雑にする二重規制
グローバル経済が急成長を続ける今、製品や原料などの海上輸送も右肩上がりで増加しています。 脱炭素社会の実現に向けたGHGの排出量削減は、世界中の海運会社が協力して取り組むべき急務といえます。
そのためには国際的なルールづくりが必要です。実際、国連の専門機関であるIMO(国際海事機関)では、国際海運のGHG排出量を2050年頃までにネットゼロに近づける目標を掲げ、2018年に初期戦略を採択、2023年に改訂版を策定しました。
ところが、EU(欧州連合)でも独自の規制をスタート。従来のEU-ETS(排出量取引制度)が2024年から国際海運にも拡大されることになりました。この制度は、EU関連航海とEU域内の港に停泊した際に排出されるGHGに対して「EU排出枠」を購入、および償却することが求められます。仮に償却が不十分であった場合には罰金や罰則があるという仕組みです。
EU規制だけでも事態は複雑ですが、今度はIMOでも「ネットゼロフレームワーク」と呼ばれる国際海運のGHG排出削減を促すための新しい仕組みが検討されており、海運業界全体がその対応に追われています。
地域規制には不公平感を生む懸念も
懸念は他にもあります。一つは、EUの制度において、国や地域による公平性が担保されていないことです。
「EU-ETSにおける排出枠購入義務は、基準値より多くのGHGを排出している企業に課せられます。 国際海運は初期段階で一定の移行期間が設けられているものの、最終的には排出する全てのGHGが対象です。 集められたお金はEUのイノベーションファンドが管理し、脱炭素の取り組みを行う企業に補助金として還元しています。 問題なのは、補助金の対象となるのがEU域内の企業に限られていること。 罰金を支払うのはEU以外の国の船会社も平等なのに、還元の対象にはなっていません」
そう語るのは、英国・ロンドンに駐在中の高曽陽平(NYK GROUP EUROPE LTD.)です。
EU域内の企業であってもイノベーションファンドから助成を受けるのは難しいという声もあるようですが、EU域内外問わず等しく規制遵守を求める一方で、資金的還元が域内企業に限定されている現状は、制度の整合性と公平性に対する構造的な課題を浮き彫りにしています。
現場レベルでの運用についても、整備していかなければならない課題があります。ベルギー・アントワープに駐在している吉田はるな(NYK BULKSHIP (ATLANTIC) N.V.)は次のように語ります。
「EU-ETSでは、EU排出枠を購入する義務があり、それを管理する口座をEU域内に開設する必要があります。ですが、手続きも国ごとのルールに則る必要があり、国によっては開設までに1年近く時間がかかりました。またEU-ETSの規制主体は、〈Shipping Company〉と規定されていますが、それは日本郵船のような船社ではなく、船主や船舶管理会社と定義されています。そのため、EU-ETSで購入するEU排出枠を管理する口座は複数となり、それら全てを管理・モニターするには手間やコストがかさみます。」
公平・中立な国際ルール実現のため、アドボカシー活動を深度化
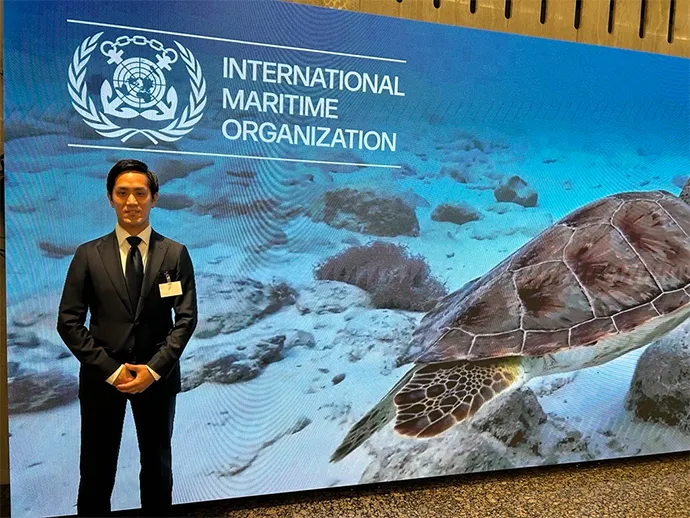
英国・ロンドン駐在の高曽陽平(NYK GROUP EUROPE LTD.)
もしIMOの「ネットゼロフレームワーク」が始まると、場合によってはEU-ETSと合わせ、二重の負担が発生する恐れもあります。望ましいのは、制度が一本化されることですが、どちらの規制が適用されることになるのか、現状では不透明です。今はIMOとEUが、お互いの様子を見ながら"綱引き"をしているような状況です。
日本郵船では、公平かつ中立な国際ルール策定に貢献するため、欧州に人員を派遣し、幅広く提言や啓発を行うアドボカシー活動を深度化。高曽と吉田はメンバーの一員です。
「国際的なルールの策定は、原則国家レベルで交渉します。日本の会社であれば日本政府との連携が重要であり、長らくIMOにおける議論に関わってきました。しかしながら2020年代に入り、特に脱炭素施策を次々と打ち出す欧州という一地域の存在感が非常に大きくなりました。実際に何が起きているのか、欧州規制の背景には何があるのか。日本郵船では現地で得られる〈生の情報〉を体得し、規制策定者である欧州委員会との距離感も重要視しています。なぜなら、現在露呈している地域規制による不平等な状態は、海運会社だけでなく、お客さまである荷主や、最終的に製品を手にする消費者など、多くの人にとっての不利益になってしまうと考えるからです。具体的には、セミナーや業界団体のイベントなどで情報を収集し、民間レベルでの提言や働きかけを業界団体と共に取り組んでいます」(高曽)
国際海運において、日系企業が現地に駐在員を派遣してアドボカシー活動を行うケースはこれまであまりありませんでした。また、二つのルールが最終的にどう整合性を取るのかという“落としどころ”も、今はまだはっきり分かりません。慣れない中で明確なゴールも見えないアドボカシー活動は、いわば手探りで進むようなものです。緻密な情報収集と冷静な状況判断も不可欠です。実に難しい業務といえます。
アドボカシー活動は、人対人の信頼関係の構築から

ベルギー・アントワープ駐在の吉田はるな(NYK BULKSHIP (ATLANTIC) N.V.)
アドボカシー活動の舞台となるのは、セミナー、カンファレンス、業界団体のイベントなど、さまざまです。
「難しさは他にもあります。一つは文化の違いです。EUといっても27の加盟国から成り立っており、それぞれ考え方が異なる場合があります。アドボカシー活動に長けている百戦錬磨のビジネスマンもいます。そんな中で私たちの話を聞いてもらうためには、人対人という関係の中で信頼してもらうしかありません。欧州委員会といってもそこにはEU市民のことを考えて政策を考えている方々がいらっしゃいます。まずは一人の人間としてリスペクトすることから始まると思っています」(吉田)
立場や考え方が異なり、時には利害関係が相反することもある相手から、いかに信頼を勝ち取るか。そこでは、日本郵船という企業ならではの強みも活かされています。
「海運業の特殊性の一つは、タンカーや自動車船、客船など、船の用途や大きさなどで業界が分かれており、多業種と密接に関わっているということです。同じ海運業を利用する会社であっても業界が違うと、お互いの立場や考え方も変わります。しかし、海運業全体で国際ルールを策定し、公平・中立性を高めるには、それら全ての業界の声を聞く必要があります。日本郵船は、さまざまな業界を網羅しており、各業界団体につながりを持っています。つまり、異なる業界の企業の橋渡し役ができるのです。これは日本の船会社特有の強みであると考えています。日本郵船に相談すれば多角的な視点を与えてくれるかもしれないという期待感が、信頼関係を構築するための力になっていると考えています」(吉田)
自動車船の国際ルールづくりでは主導的な役割を

RORO船のGHG排出量計算ガイダンスを策定しているSFCのイベントにて。 茂住洋平(日本郵船・脱炭素グループ)の姿も見える(最前列中央)
日本郵船のアドボカシー活動は、IMOやEUといった大きな枠組みだけでなく、特定の船種の課題についても行っています。
例えば、自動車を海上輸送する外航RORO船※におけるGHG排出量計算ガイダンスの策定プロセスに関するアドボカシー活動もその一つです。担当しているのは茂住洋平(日本郵船・脱炭素グループ)です。
外航RORO船のGHG排出量削減のルールをつくるためには、そのもととなる排出量を算定するための基準が必要です。しかし、外航RORO船には、これまで統一した算定方法がありませんでした。
「その理由はRORO船の特殊性にあります。 例えば、製造国から販売国に輸送する場合、往路は自動車を満載するのに、復路は積み荷が無い状態になったり、また、途中で一部を積み降ろし、そこからまた別の国へ向かったりといったケースもあります。 排出量の計算は、航路毎の排出原単位(GHG排出量/(輸送量×輸送距離))を各船会社が算定し、それに荷主が「積荷重量×輸送距離」を乗じて算出します。 RORO船の特殊な事情から、航路毎の排出原単位を算出するためにどの港からどの港までの情報をもとに算出するかが、船会社によってばらばらだったのです。 これでは公正な競争ができません。 環境責任を可視化し、社会的な信頼を獲得するためにも、世界基準に則った統一された算定ガイダンスが必要です」
当初は日本海事協会、ワレニウスウィルヘルムセン(スウェーデン/ノルウェーに本拠を置く海運会社)と日本郵船が中心となり、業界団体などへのヒアリングを実施し、課題を探りながら算定基準の策定の必要性について議論を重ねていました。
企業の利益のためではなく、業界全体の未来のために
すでに欧州では国際的なNPO法人のSmart Freight Centre(SFC)が策定した物流のGHG排出量算定方式に関するガイダンスがまとめられており、ISO化もされ、業界のスタンダードになりつつありました。 ただしこのガイダンスは大枠で陸・海・空の全ての輸送モードを網羅した内容であり、外航RORO船を考慮した算定方式にはなっていませんでした。 その点は、SFCとしても課題意識を持っていました。
「彼らも同じ課題を抱えているわけですし、ならば一緒に取り組んだ方がいいと考え、声をかけたわけです」(茂住)
日本郵船も同NPO法人へ加盟し、外航RORO船のGHG排出量算定の標準化を目的とした「Global Ro-Ro Community」(以下GRC)をSFCの傘下に立ち上げ、策定のための議論を1年かけて行いました。GRCに参画する企業は次第に増え、加盟船社の船腹量は世界の自動車輸送能力の約8割を占めるにいたっています。議論の透明性を保つために、GRCメンバー内の議論に留まらず、荷主や他のステークホルダーとも定期的に議論内容を共有し、フィードバックを交わす透明性の高い議論を経て、世界標準となる中立・公平な外航RORO船のGHG排出量算定ガイダンスを策定し、2025年5月に開示しました。
「高曽や吉田のアドボカシー活動と同じで、単なる企業活動ではなく、世界の海運業全体の未来に向けた取り組みです。粘り強く対話を重ねていく仕事は苦労も多いのですが、脱炭素社会の実現に向けた礎を築いているという自負もあり、大きなやりがいを感じています」(茂住)
地道なアドボカシー活動を通して日本郵船が目指すのは、国際海運業界全体が公平かつ効果的に脱炭素に取り組める環境づくりです。地球環境の保護と経済活動の両立を図る壮大な挑戦は、これからも続いています。

本店会議室にて。高曽や吉田は現地から参加。
※RORO船:Roll-on Roll-off ship。貨物を積んだトラックやシャーシ(荷台)ごと輸送できる船舶。






