テスト・エンジンが稼働 グループの技術力結集、新燃料の検証を短期化
公開日:2025年05月16日
更新日:2025年10月15日
日本郵船は足元から船舶の温室効果ガス(GHG)排出量を削減するため、既に普及しているか、普及が始まりつつある新たな燃料の活用を進めている。その一つがバイオ燃料だ。使用に当たり要となる施設が2024年10月に千葉県内に開所した。アンモニア燃料タグボートに生まれ変わる前の“魁”に搭載されていた発電機を再利用してテスト・エンジンとして設置し、バイオ燃料を従来型エンジンで使用する際の安全性について評価する。日本郵船グループの技術力が結集した施設でもある。
足元からGHG排出削減
バイオ燃料とは廃食油など生物由来の有機性資源を原料とした燃料のこと。原料の植物が成長過程で大気中の二酸化炭素(CO2)を吸収するため、燃焼時のCO2排出量は実質ゼロとみなされる。既に普及している代替燃料のLNGなどは専用のエンジンを搭載した船にしか使用できないが、バイオ燃料は既存のエンジンで焚ける「ドロップイン燃料」。大きな追加投資が不要であることや、重油燃料に混ぜて使用できるといった特徴から、過渡期にCO2をはじめとするGHGを削減するのに有効な手段となる。
現在船舶で使用されているバイオ燃料はバイオ分を24%、重油を76%の割合で混合した「B24」が主流。日本郵船は19年から使用を始め、補油港や船種を徐々に広げてきた。24年12月末までに200回を超える補油を実施している。24年4月には長期のトライアルプロジェクトを立ち上げ、これまでの短期から長期間の使用で、総合的な検証を行う段階に入った。
これまでに日本郵船が使用したB24のバイオ燃料の安全性は、燃料油分析や化学製品の製造などを手掛けるグループ会社、日本油化工業のラボでサンプルを分析したうえで、社外エンジン設備での試験・分析や、日本郵船の運航船で少量ずつトライアル使用しながら確認してきた。このため評価期間は1~2年に及んだが、自社のテスト・エンジンを導入したことで、あえて負荷をかけた検証やバイオ分100%での検証も行いやすくなり、試験期間を2~3カ月へと短縮できるようになった。各国の環境規制やバイオ燃料をはじめ新燃料の需要増加に対応するには、試験期間の短縮や試験に要するコストの削減がカギとなるが、この陸上施設がそれを実現する。
「バイオ残渣」の可能性探る
テスト・エンジンで品質を検証する対象の一つが「バイオ残渣(ざんさ)」。聞きなれない言葉だが、通常のバイオ燃料から“グレードダウン”した燃料になる。バイオ燃料を精製する過程で副産物としてでてくるもので、可燃性の液体だが通常の燃料よりも取り扱いが難しいとされる。海外の一部では使用実績があるというが、本格的な品質の検証はこれから。そこに日本郵船はグループを挙げて挑戦する。
海務グループ機関チームの植松将史チーム長は「バイオ残渣は通常のバイオ燃料よりも安価になると見られ、かつ、GHG強度(エネルギー当たりのGHG排出量)は通常のバイオ燃料と同様になるはず。バイオ残渣を安全に実運用できるようにすることが直近の目標だ」と話す。
検証の進め方はこうだ。まずはサンプルを取り寄せて、日本油化工業(※)のラボで成分や性状を分析し、通常の重油燃料と比べて特異な点がないかを確認する。そのうえで、テスト・エンジンで実際に使用してみて技術的な検証を行う。
バイオ残渣には温度変化で固形化するものもある。「船で使う時にタンクや配管で冷えて固まることがある。固形化しやすいものは燃焼時に煤が出やすい傾向にあるので、実際にテスト・エンジンで焚いて確認していく」。こう話す植松氏は船のエンジンを動かす機関部で経験を積んだ機関長。テスト・エンジンでの検証には植松氏をはじめ船舶運航のプロである機関士が立ち合い、慣れ親しんだ重油燃料との違いや、それによって引き起こされるエンジン・トラブルの有無を一つずつ検証していく。海上勤務の経験が活きる。
また、通常のバイオ燃料についても、これまでに使用してきたB24のみならず、バイオ分100%の「B100」の燃焼評価試験も実施し、船舶で使用した場合の課題の有無などを検証して来るべき需要に備える。
(※)日本油化工業:化学技術を中心とする日本郵船の研究機関
「作り・動かし・調べる」がグループで完結
バイオ残渣の検証における第一のポイントは、その燃料でエンジンを安全に回せるかどうか。続いて、排気系統に問題が生じないかどうか。さらに、「バイオ燃料は“生もの”なので劣化しやすいと見られる。バイオ燃料は劣化すると酸を生じ、部品の腐食トラブルにつながる」(植松氏)とみて、燃料や排気から煤を集め、日本油化工業で分析を行った結果を見極める。

“魁”に搭載されていた発電機を再利用したテスト・エンジン

低温で固形化したバイオ残渣。テスト・エンジンで検証
以前であれば本船から取り寄せる必要があった煤もテスト・エンジンができたことでその場で収集し、トラブルの原因になりそうなポイントの分析、評価の時間を飛躍的に短くできるようになった。目まぐるしく変化する環境対応に従来からスピード感が要求されていたが、相当の期待に応えることができそうだ。
性状分析データと、テスト・エンジンで得られたデータを基に、船上保管、混合安定性、機器への影響、排ガスといったポイントで検証をしたうえで、運用マニュアルを作成し実運用に進める。さらに本船で得られたデータを運用マニュアルにフィードバックすることでトラブル・ゼロを目指す。
日本油化工業の竹田充志技術研究所長(工学博士)は「バイオ燃料は化学処理して作られた燃料。完璧に化学処理されていれば劣化したり酸を生じたりする程度は少ないだろうが、バイオ残渣の性質はまだわからない部分が多い。研究を進めていく」と話す。
日本油化工業はエンジン・トラブルの原因となる燃料の固形化を防ぐ添加剤も開発・提供している。性状分析データやテスト・エンジンでの使用で何らかのトラブルが明らかになれば、それを解決するための新たな添加剤の開発にもつなげる。
テスト・エンジンなど施設内の機器の設計・施工を担当したのは日本郵船グループのエンジニアリング会社であるボルテック。“魁”に搭載されていた発電機を自社の工場でオーバーホールしたうえで、施設に設置した。
新しい燃料を検証するだけに、テスト・エンジンに不具合が生じることも想定されるが、その時のメンテナンスもボルテックが受け持つ。ソリューション・エンジニアリング事業部営業グループの鳥海真澄スタッフグループ長は「最新の燃料を使用した場合のエンジンの状態を実際に目にできる機会になる。実際に稼働しているテスト・エンジンがあることで、当社自身もメンテナンスに対するスキルアップに役立てられる」と期待する。
テスト・エンジンが稼働すると、船内のエンジンルームさながら、会話ができないほどの轟音に包まれる。しかし、扉の外へ一歩出るとわずかに音が漏れるだけ。実際にエンジンを動かして燃料をテストする施設だけに周辺への騒音やにおいに配慮して住宅地から離れた場所に施設を置いたが、気密性の高い建屋によって騒音対策は万全だ。ボルテックが建屋の建築も担当した。「当社は陸上発電設備のメンテナンスでも経験があるので、規則対応、届け出などの手続きをする上でもその経験が活きた」(鳥海氏)
グループが持つ技術力を有機的に結び付けて新燃料へと挑むこのプロジェクト。燃料分析、添加剤開発、テスト・エンジンの運用、メンテナンス。さまざまな技術の結集が、新たな燃料による船舶の低・脱炭素を実現する力となり、日本郵船グループ運航船の安全の礎となる。

バイオ燃料の長期使用試験航行を行ったVLCC“TENJUN”
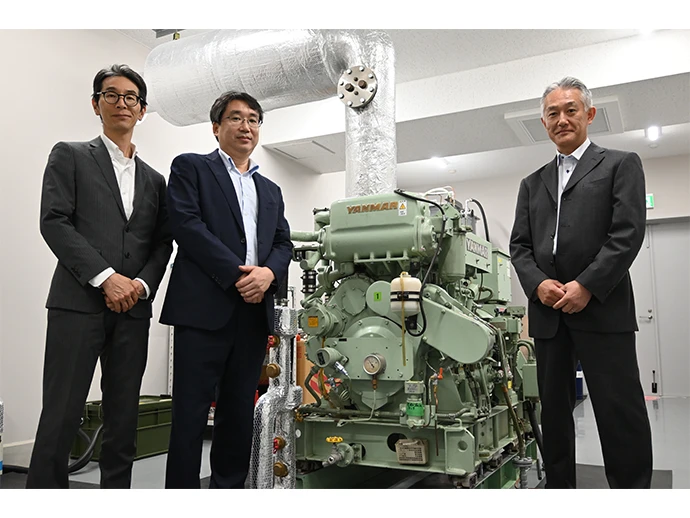
グループの力を集めテスト・エンジンを回す。左から、鳥海氏、植松氏、竹田氏
プロジェクト担当者に聞く
新たな技術は
既存技術の上に築かれる
植松将史 氏
海務グループ機関チーム長、機関長
—— 植松機関長のこれまでのキャリアについて教えてください。
機関長として登用されるまで、約10年間一度も陸上勤務をせず海上勤務をしました。初めての陸上勤務は、シンガポールにある当社グループの船舶管理会社であるNYKシップマネージメントで、しばらく船舶管理業務を行った後、シンガポール現地法人のNYKグループ・サウス・アジアで営業海技としてコンテナ船の船主業務を担当しました。その後海上勤務をはさみつつ、海務グループ機関チーム、グループ会社のMTI(Monohakobi Technology Institute)、そして現職2回目の海務グループ機関チームへの配属がこれまでのキャリアになります。
—— 現在携わられている、テスト・エンジンによるバイオ燃料の安全性評価の業務について教えてください。
2024年10月1日、千葉県内に試験用エンジン設備を新設し、新燃料を内燃機関で運転する際の安全評価を行っています。現在は主に「舶用機関で新たなバイオ燃料を使用すること」と「バイオ燃料継続使用による影響」の定量評価を行うことを目標に、この試験用エンジンで運転データを集め分析します。これまで船上で行ってきたトライアルのフェーズを陸上のテスト機を使うことで、導入までの時間を大幅に短縮することを目指しています。
このように、さまざまな条件・環境が重なり、世間の追い風が吹いたことで実現に向けて動き出した陸上のテスト機ですが、担当者としては「やってみないとわからない」、「やらなきゃ進まない」という気持ちで、不安要素を一つずつ丁寧に解決してきました。前例のないプロジェクトを進めるには、過去のMTIや機関チームでの経験が活きています。特にMTI時代から抱いていた「どうやったら試験用エンジンを持てるか」という想いは、このプロジェクト実現に向けて大きな心の支えになったと感じています。
こういったこれまでにないことを実現する新たなプロジェクトでは、多面的に課題や可能性を広く検討し、切るものは切って、進む方向を決める「取捨選択」が必要です。マクロとミクロの視点から、プロジェクト全体を見渡して、優先事項を都度判断していく必要性を改めて認識しました。
—— 大切にしている心構えはありますか。
私がエンジニアとして大切にしている考え方は、「技術に対しては真摯に」「安易に流されない」の二つです。「技術に対して真摯に」という意味は、われわれのフィールドであるエンジニアリングは、物理法則で動いているものを常に相手にします。機械は嘘をつきません。真摯に担当者が向き合えばちゃんと返ってくるし、逆に真摯さが欠ければいつかしっぺ返しを受けます。「技術や機械に真摯に向き合うこと」は、エンジニアの必須要件だと思います。
もう一点の「安易に流されないこと」、これは「営業海技時代」や「本船で目の前の機器を整備するとき」も、そして「新しいことを開発する場合」や「技術部門に身を置く現在」であっても、根拠のない雑音やその場限りの無責任な発言に簡単に流されないことを指します。特にエンジニアは「いつでも冷静に、本当に必要なことを見極める力」を持つように心がける必要があると考えています。目の前のことが「エンジニアとして信じられる事実」と異なるのであれば、戦うつもりで挑む。もし、本当に大切なことをしないで、安易に流されれば、それは何の解決にもつながっておらず、将来の仲間たちに問題を先送りしているだけです。
—— 若手の海技者に伝えたいことはありますか。
機関士の皆さんは、エンジニアとして知見や経験、知識を粛々と積み重ねていってほしいと思います。新技術は既存技術の上に築かれるものです。現在は、過去には想像もつかなかったくらい環境が変化しており、例えば燃料の変化がその最たる例ですが、アンモニア燃料を取り扱うにあたっては、同じガス系燃料であるLNGの取り扱いを参考にしますし、その他これまでの経験や知見を積み重ねた上で、これを応用して作り上げています。新燃料だからといって、全てゼロから何かを生み出すわけではありません。工学的にも、新技術は現技術の上に積み上げられるもの。このため、日々積み重ねていく経験や知見が大切になります。
2025年3月25日発行の海事プレス増刊号を再編集






