世界初のアンモニア燃料船を創る海技者の視点、安全対策に活かす
公開日:2025年05月14日
更新日:2025年10月15日
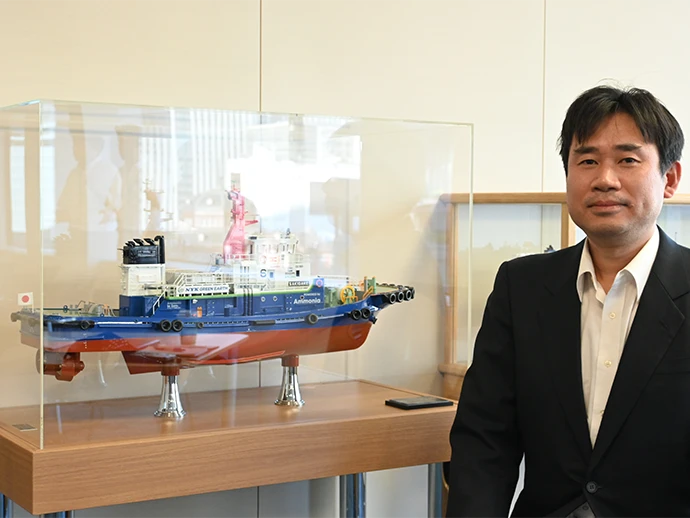
2024年8月、世界初の商用利用を前提としたアンモニア燃料船が東京湾に就航した。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のグリーンイノベーション(GI)基金プロジェクトで、日本郵船とIHI原動機が日本海事協会(NK)の協力を得て開発したタグボートだ。15年にLNG燃料船の先駆けであれとの思いから“魁(さきがけ)”と名付けられたこの船は、次世代燃料のアンモニアを使用できる国産エンジンを搭載して生まれ変わった。もとの船名を受け継ぎ、アンモニア燃料時代へと帆を進める。

日本初から世界初へ

アンモニアはもともと肥料などの化学原料としては一般的で、日本郵船も以前から貨物としてのアンモニアの輸送に携わっていた。近年は燃焼時に二酸化炭素(CO2)を排出しないという特性が注目され、船舶の燃料としても世界的に活用が模索されている。
日本郵船が船舶燃料としてのアンモニアへの取り組みを本格的に始めたのは2020年だった。その翌年10月にはエンジンメーカーや造船所などの関係企業と連携する「アンモニア燃料国産エンジン搭載船舶の開発」がNEDOによるGI基金事業として採択された。この事業の第一弾として開発されたのがアンモニア燃料タグボート(A-Tug)の“魁”だ。同船の前身は国内初のLNG燃料船として建造されたタグボート。横浜港を中心に約8年間の安全運航と通算183回のLNG燃料の補給を終えて、23年10月から日本郵船グループの京浜ドック追浜工場に入渠、24年にかけてアンモニア燃料船へと改造された。
主機関などをアンモニア燃料仕様へと換装する改造プロジェクトは、LNG燃料タグボートを開発した主要メンバーが再び集結し、オールジャパン体制で進められた。IHI原動機がアンモニア燃料主機の開発・製造・試験運転を担当し、24年5月に舶用4ストロークエンジン実機として世界初となるアンモニア混焼率80%での燃焼試験に成功。NKは22年7月にアンモニア燃料タグボートの基本設計承認(AiP=Approval in Principle)を行うとともに、安全性に関する技術検証や法規制対応などで支援した。アンモニア燃料の供給は発電大手JERA、化学メーカーのレゾナックと連携し、横浜港内においてタンクローリーから船へのトラック・ツー・シップ方式で実施する体制を整えた。
世界初の商用アンモニア燃料船を新造船ではなく改造で実現したのは、既存船の船殻を再利用することで工期短縮をねらい、世界初を目指したことが理由の一つだった。また、CO2排出削減が従来の重油燃料と比べて25〜30%程度のLNG燃料船が2050年のゼロエミッションに向けて全てスクラップされるのかという疑問もあったことから、改造という挑戦を選択した。さらに、就航後にアンモニア燃料船へと換装することが準備されている「アンモニア燃料レディ船」の実現性を技術的に見極め、知見を得ることも目的だった。
改造を終えた“魁”は日本郵船グループの新日本海洋社によって東京湾での曳船業務に従事している。改造プロジェクトと実運航から得た知見を基に、次なるアンモニア燃料船の開発も進められている。
2番船には燃料供給設備が不要という理由からアンモニア輸送船を選んだ。“魁”が内航船であるのに対して、今度は外航船だ。こちらもGI基金事業「アンモニア燃料国産エンジン搭載船舶の開発」の一環で、4万立方メートル型のアンモニア燃料アンモニア輸送船(AFMGC=Ammonia-fueled Medium Gas Carrier)をジャパンエンジンコーポレーション、日本シップヤード(NSY)、IHI原動機、NKとともに開発しており、26年11月にジャパンマリンユナイテッド(JMU)の有明事業所で完成予定だ。外航船のネットゼロエミッション達成への貢献につなげるため、船全体で温室効果ガス(GHG)を80%以上削減することを目指す。


安全を自ら創り出す
「積極的に高い水準の安全を自ら創り出していこうと取り組んできた」。鹿島伸浩専務執行役員・技術本部長はこう語る。アンモニアを船舶の燃料として実用化するためには、克服すべき技術課題が大きく3点あるとされる。難燃性の解決、温室効果を持つ亜酸化窒素の処理、そして毒性だ。
特に気を遣うのが毒性への対応になる。漏洩などで乗組員らの安全が脅かされないよう、万全の対策を取ることが、アンモニアを燃料として使用、普及させる上での重要なポイントになる。日本郵船によるアンモニア燃料船の開発プロジェクトでは、海運、造船、エンジンメーカー、船級協会が知見を持ち寄ることで、ハードとソフトの両面から毒性の克服に向けた安全対策を検討してきた。どこから漏洩するリスクがあるかを洗い出し、配管などからの漏洩をいかに防止するか、万が一漏れたときにどう検出するか、どのように対処するかを、シミュレーションしながら検証してきた。その結果、アンモニアを燃料として安全に使用する道にめどをつけた。
安全対策は、船のハード面だけでなく、運航管理マニュアルの策定や、アンモニア燃料関連機器のメンテナンス手法の確立など、ソフト面でも多岐に及ぶ。その検討には海技者の視点がふんだんに盛り込まれた。船のエンジンを扱うプロである日本郵船の機関長・機関士がタスクフォースを結成し、海技者の目線でリスク評価や安全対策を検討。従来の船と仕事の仕方やプロセスを変える必要性も視野に入れながら対策を提言した。これらを機関室の配置や仕様などに反映させていった。
「できるだけ機関室に入らないようにするためにカメラを増設し、機関室の温度や圧力を遠隔で監視できるようにする。従来の船の機関室の様子とはかなり異なるものになる」と、タスクフォースで取りまとめ役を担った海務グループ調査役で機関長の髙森直人氏は話す。

普及に向け供給設備の開発も
貨物としてアンモニアを輸送する船は自らのタンクから燃料としてのアンモニアを入手できるが、他の船種では燃料アンモニアの調達が必要になる。燃料のサプライチェーンを構築することが、アンモニア燃料船の普及にとって不可欠になることから、日本郵船はアンモニア燃料の供給事業への進出も目指している。その中で、燃料としてのアンモニアを供給するための船や、アンモニア燃料供給船からアンモニア燃料船へと液体の燃料を安全に移すための装置「バンカリングブーム」の開発を進めている。
バンカリングブームは、原油や天然ガスなどの液体の荷役機器製造で国内シェアトップのTBグローバルテクノロジーズ(TBG)と共同で開発を進めているもので、24年9月にアンモニア燃料向けで世界初となるAiPを取得した(TBG調べ)。日本郵船はAiP取得に際して、自社開発のアンモニア燃料供給船の設計データのほか、筆頭株主として出資するセントラルLNGマリンフューエルが運航する国内初のLNG燃料供給船“かぐや”やアンモニア輸送事業で得たアンモニアの取り扱いに関する知見を提供した。
このバンカリングブームの最大の特徴は、アンモニア燃料供給船とアンモニア燃料船の接続を緊急時に瞬時に切り離せること。TBGが開発した装置を搭載することで、緊急離脱の際のアンモニアの飛散量を大幅に抑えることができる。毒性のあるアンモニアを安全に供給する仕組みだ。
日本郵船はアンモニア燃料船の開発を「船舶の脱炭素化における一丁目一番地」と位置付け、さまざまな船種にアンモニア燃料を導入していく計画。33年までに計15隻のアンモニア燃料船の竣工を目指しており、20年代後半以降には自動車船もしくはバルカーを建造し、35年頃から他の船種も含めてアンモニア燃料船隊を拡大していく。
1番船“魁”で得たアンモニア燃料船の知見を2番船以降の外航船の建造と運用・ルールづくりに役立てていく。脱炭素に向かうブリッジソリューションとしてのLNG燃料に続いて、ファイナルソリューションのアンモニア燃料でも業界の“魁”になることを目指す。
アンモニア燃料の国産エンジンを搭載したA-TugとAFMGCのプロジェクトは日本の海運会社、エンジンメーカー、造船所、船級協会が一体となり、エンジンの開発、本船の建造、商業化までを一貫して進めており、ここから得た知見・技術を広く公開する予定だ。これにより自社のみならず、日本や世界の船舶の脱炭素化に貢献していく考えだ。
プロジェクト担当者に聞く
嗅覚を磨き、新技術に対応
髙森直人 氏
海務グループ調査役、機関長

——髙森機関長がアンモニア燃料船に関わることになった経緯を教えてください。
当社がタグボートとアンモニア輸送船という二つのアンモニア燃料船開発プロジェクトに取り組む中、営業部門や建造に関わる工務部門に加えて、船員・海技者の知見と経験を詰め込んだ安全な船にする必要性から声がかかりました。
私は海上勤務でVLCC、海洋調査船、コンテナ船、LNG船、鉄鉱石船など十数隻に乗船した経験があります。陸上勤務では新造船業務、組合専従、コンテナ船の船主業務に携わりました。アンモニア燃料船はアンモニアを燃やして動力を得るという新しいチャレンジですので、エンジンメーカーや造船所とともに検討と検証を繰り返しながら取り組みます。関係者はメーカーのみならず、行政機関や港湾局、アンモニア供給会社など多岐にわたりますので、海技者としての知見や経験を植え込むことはもちろんですが、陸上勤務の経験を活かして関係者の調整業務も担っています。
——機関長・機関士がアンモニア燃料船の安全対策を提言したとうかがいました。
30人ほど集まってアンモニア燃料の安全対策を検討し、そのアイデアをまとめたレポートを22年春に作成しました。当社にはLNGをはじめとするガス焚きエンジンの経験があり、それに沿っていればアンモニアにも対応できるというベースはあるものの、LNG燃料との大きな違いとして毒性と腐食性があります。特に毒性については、乗組員の健康被害を防止するためにこれまでとは異なる注意が必要になります。
このため、まず経済産業省が公開している陸上で発生した過去の事故例などを調べ、どのようなかたちで事故が起きているのかを頭に入れました。調べていくにつれて、技術者が勉強を重ね、安全な取り扱いの知識が蓄積されてきた歴史を知ることもできました。アンモニア関連施設の視察や携わっている方々へのヒアリングも実施しました。そこから導き出した安全対策やメンテナンス手法などをアンモニア燃料船の設計に取り入れ、運航に活かしていきます。
——アンモニア燃料船の開発に当たっての課題は。
技術的な課題はもちろんあり、想定外のことが日々起こりますが、当社や各社からプロジェクトに参加しているメンバーが50~60人おり、皆で集まると解決のアイデアが出てくるので非常に有難いです。
——アンモニア燃料船で実現したいのはどのようなことですか。
まずは安全第一。何らかの事故が起きれば、船舶のアンモニア燃料は技術的には早熟ではないかというイメージがついてしまい、当社だけではなく世界中の脱炭素が遅れる恐れがあるからです。
——日本郵船の海技者として働くことの魅力を教えてください。
アンモニア燃料船“魁”を世界に先駆けて就航させたように、脱炭素に向けたあらゆる対策を模索し、実現できる会社はそうないと思います。当社が経営計画で進めている両利きの経営に沿って、モノ運びの深度化と新技術の両方に関われることは大きな醍醐味です。
今は過去の経験を活かしながら、全く新しいことに取り組まなければならない時代です。鼻を利かせて新技術を取捨選択する必要もあります。技術者としての嗅覚を磨くには、日々船上の課題に悩んだり、燃料節約や安全性向上のアイデアを考えたりすることの積み重ねで技術力を高めていくしかありません。技術を磨いておけば、新たな課題にも柔軟に対応できると考えています。
——一人前の海技者を目指す若手に伝えたいことはありますか。
私は現在、アンモニア燃料船を担当していますが、アンモニア自体、7~8年前にはエネルギーとして想定されていなかったものです。同様に将来、経済性と環境を両立できる新技術により、これまでにない動力が生み出されるかもしれません。顧客の荷物をお預かりして、安全・安定的に運航するモノ運びは海運の基本であり、古からの海技の伝承や技術を大事にしなければいけません。それと同時に、常にアンテナを高く張り、新しい技術に柔軟に対応できる海技者が求められています。これに応えることは大変ではありますが、これまでに類のない唯一無二の存在になるチャンスでもあります。船乗り魂で頑張ってもらいたいと思います。
2025年3月25日発行の海事プレス増刊号を再編集






