日本郵船が創薬資源の探索に協力。海の恵みで人類の未来を照らす
公開日:2025年10月10日
更新日:2025年10月20日

船底に付着する“厄介者”が、未来の薬になるかもしれない−−。日本郵船は中央大学と共同で、未知の有用物質を探し出して創薬につなげる前例のないプロジェクトを進めています。日本郵船だからこそ実現できる発想とスケールで、海の恵みを利用して人類の未来を照らす挑戦にご期待ください。
海洋生物から創薬資源を発見するという発想
中央大学と日本郵船が共同で取り組むプロジェクトの意義や今後の展望を、研究を主導する中央大学理工学部准教授の岩崎有紘先生、日本郵船イノベーション推進グループの大東鷹翔、船長の山中遼に聞きました。
――プロジェクトの概要と目的
大東:日本郵船は経営の中心に「サステナビリティ」を据えています。具体的には「海、地球、そして人々への恩返し」をテーマに、「NYKグループサステナビリティ イニシアティブ」という枠組みを設け、有志社員による発案も含めた多くの取り組みを通して社会や環境の課題解決に取り組んでいます。今回の中央大学と日本郵船の共同研究は、海洋生物から薬のもとになる物質を見つけ出し、人類に役立つ価値を明らかにするのが大きな目的です。日本郵船は、船底付着生物の「採集環境」をコーディネートする立場でプロジェクトに参加しています。

イノベーション推進グループの大東鷹翔
――構想は10年以上前、「NYKグループサステナビリティ イニシアティブ」によって実現
岩崎先生:私の研究は海洋生物から薬のもとになる物質を探すことがテーマです。プロジェクトの着想は10年以上前。日本郵船の山中船長と私は高校の同級生です。お互いの仕事の話をしていたときに、山中船長から「船底には海洋生物が大量に付着して燃費や速力性能を悪化させるので、数年に1回こそぎ落として廃棄する作業が発生する」という話を聞きました。これを海洋生物の採集に利用できないかと考えました。

中央大学理工学部准教授の岩崎有紘先生
山中:岩崎先生から初めてアイデアを聞いたとき、非常に夢のある話だとは思いました。しかし当時はこれを実現させる方法が思いつかず、具体化しませんでした。
それから10年以上がたち、本店で勤務していたとき、日本郵船では社会課題解決に挑戦する「NYKグループサステナビリティ イニシアティブ」という活動が始まりました。そんな中、岩崎先生と久々にこのアイデアの話になったとき、このスキームで実現できるのではないかと思い企画化して応募しました。
幸い社内のリアクションも好意的で、「NYKグループサステナビリティ イニシアティブ」の事務局となるサステナビリティ経営グループの協力を得て、まずはアイデアの実証実験をすることになりました。実はその頃すでに陸上勤務から船(海上勤務)に戻ることが決まっていたのですが、当時同じグループだった大東が加入し、このプロジェクトに興味を持ってくれたので、うまく引き継ぐことができました。

山中船長は本インタビュー時乗船中、パナマ運河より
大東:正直「私が担当になった途端成果が出なくなっては大変だ」という変な緊張感がありました(笑)。世界的に例がない取り組みなので行動力が求められる案件なのですが、山中が戻ってくるまでに成果を上げておきたいと思いました。実証実験に成功して、こうして一般に公表できるプロジェクトになったことは、非常に感慨深いですね。
海運会社だからこそできる効率的な採集方法
岩崎先生が注目しているのは海洋生物が独自に持つ天然物。採集作業の非効率性は長年の課題でしたが、日本郵船との出会いで難題は一気に解決へと向かいます。
――なぜ海洋生物に着目するのか?
岩崎先生:過去40年間に承認された新薬の内、およそ半分は生物がつくる化学物質(天然物)からヒントを得て開発されています。つまり、新しい天然物を見つけることで医薬品の開発が飛躍的に加速する可能性があるということ。
2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智先生は、静岡にあるゴルフ場の土の中に生息する微生物から病気の特効薬のもととなる物質を発見しました。何もヒマラヤやアマゾンの奥地でなくとも、ごく身近な環境に画期的な物質を持つ生物がいるかもしれないのです。
陸上の植物や微生物は、比較的古くから研究が進んでいるので、未開拓の部分が多くポテンシャルの高い海洋生物に着目しています。具体的には海洋環境が豊かな沖縄や奄美地方のサンゴ礁に生息する生物を対象に研究を進めてきました。
――これまでの海洋生物の採集方法
岩崎先生:これまでは学生と一緒に現地に赴き、手作業で海洋生物を集めていました。これが過酷な作業で、まず広大なエリアに点在する生物を探す必要がある上に、潮が大きく引く干潮の時期(3月〜7月頃)の大潮の日だけに作業が限られる。しかも、1日の内でも作業できるのはわずか4時間ほどです。1日1 kg程度しか採集できない日もあります。そのような中でも、抗がん剤への応用が期待できる新規物質の発見といった研究成果を上げているだけに、やりがいのある作業ではあるのですが、非効率性は長年の課題でした。

従来の採集風景。手間暇のかかる地道な作業
――船底付着生物の採集への水先案内人
山中:船底付着生物からの天然物探索の実証実験では、まず手はじめに日本郵船グループの船底クリーニングダイバー会社や、助燃剤のメーカー、タグボートの造船所などから船底付着生物のサンプルを提供してもらいました。その結果、狙っている生物の採集には稼働時間が長い船よりも、むしろ係留状態の長い船や海上構造物の方がさまざまな面で都合が良いことが分かりました。
しかし、そのような環境に生息する生物サンプルを日本郵船グループ内だけで集めるのには限界があります。そこで生物サンプルを中央大学に提供するのではなく、自社の持つ海事ネットワークを活用して、船底付着生物の採集活動をコーディネートするというスキームに変更しました。海事産業の現場で採集を行うには、どこにどのような現場があるのか、といった情報はもちろんですが、それ以外にも安全に採集を行うためのノウハウが欠かせません。
日本郵船が採集活動をコーディネートすることで、中央大学はこれまでアクセスできなかった海事産業の現場での採集が可能になります。具体的には、採集したい生物がいそうな船や現場を見極め、採集活動の段取りを整え、採集活動時の安全監督を行っています。いわば、船や海事産業の現場での採集のための「水先案内人」のような役割を担っています。
――船底付着生物からの天然物探索
岩崎先生:これまでは限られた時間の中で悪戦苦闘していましたが、時期や時間を気にせず採集できるようになったのは、まず大きなメリットです。長崎での採集では、たった2時間で35kgの船底付着生物を入手でき、圧倒的な効率化につながりました。また、実証実験中に沖縄で採集した生物サンプルからは新規物質も発見できました。解析したところ、この新規物質がアフリカ睡眠病の原因となる病原生物の増殖を抑えることが分かったのです。

岩崎先生の研究室にて。プラスチックのバケツに保管されている海洋生物のサンプル
“厄介者”だった船底付着生物が“宝物”に変わる
――プロジェクトの持つ価値
岩崎先生:海洋生物を集めていると、現地の人たちは「なんでこんなものを集めるの?」と不思議そうな顔をします。しかし私たちが研究に使うことを説明すると、皆さん協力的になってくれます。誰かにとっての“厄介者”が思いがけない価値に変わるところが、このプロジェクトの面白いところです。
山中:実際、びっしりと貼り付いた船底付着生物は船乗りにとっても陸上の運航業務担当者にとっても、間違いなく“厄介者”。これが「画期的な薬のもとを見つけるための宝の山」になるかもしれないということは、このプロジェクトが社内で多くの方から応援された一番の理由となっています。
岩崎先生:採集後の研究過程では、微生物がつくり出す1 mgや0.1 mgといった微量な物質を扱う分、繊細で緻密な作業を必要とします。分子構造を解き明かす構造解析のプロセスは、この研究のクライマックス。自分の解き明かした分子構造を既存の化学物質のデータベースと照合し「ヒットなし」と出る。これまで生きてきた全ての人類が知らない物質を自分だけが知っている瞬間に立ち会えるというのは、非常に大きなやりがいにつながります。
山中:今後AI(人工知能)の発展で創薬のアプローチ方法が大きく変わるかもしれません。しかし、自然界の深遠な部分まで含めると、AIで生物多様性の全てを解き明かすことはやはり難しいと思います。その神秘に挑んでいるのが岩崎先生の研究であり、その価値は普遍的ではないでしょうか。
岩崎先生:天然物は、何億年もの生命の営みが凝縮された物質。生物が生存競争を勝ち抜くための知恵が隠されているに違いありません。私たちの身体は非常に複雑であるため、人間が科学的にデザインした物質では、狙った作用が出なかったり、予想外の副作用が起きてしまったりすることがあります。ですので、自然界がつくり出した天然物に学ぶことが重要だと思うのです。天然物をうまく活用することが、きっと人類に役立つ創薬の近道になるはずです。
日本郵船がサポートする創薬という“未来への航海”
中央大学との実証実験は2022年に始まり、成果を得たため2025年に共同研究契約を締結することになりました。
――プロジェクトの展望について
大東:プロジェクトの稼働期間は5年間。新薬に結び付く物質の発見は簡単ではないと思いつつも、プロジェクト延長に向けて、なんとか成果を上げていきたいですね。今後さらに多くの協力先を見つけることで、採集する機会を増やしていきます。
岩崎先生:真に画期的で価値のある物質は10年に一つ見つけ出せればいい方だともいわれています。さらに薬になるまでの成功率は、3万分の1とも。そう考えると気の長い取り組みが必要になります。ですので、新薬というゴールにはたどり着かないとしても、新しい物質の発見など学術的に意味のある成果を導き出すことが大事だと考えています。私と一緒にプロジェクトを動かしてくれた日本郵船の山中船長、大東さんの情熱には、本当に感謝しています。
山中:私たちが取り組んでいるのは、“思いがけない出会いの塊”のようなプロジェクトだと考えています。今後もどんどん日本郵船のネットワークを駆使して、新しい出会いを重ねていくことで、次の5年につなげていきます。
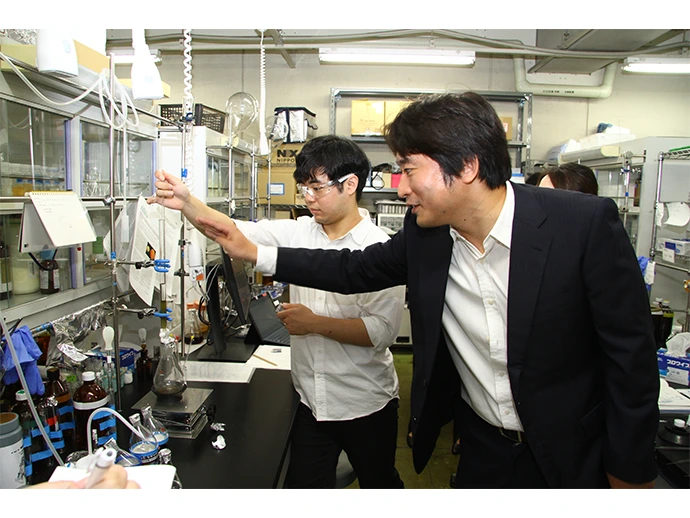
海洋生物から新薬の種を見つけるため日々研究
<関連リンク>
中央大学 生物有機化学研究室







