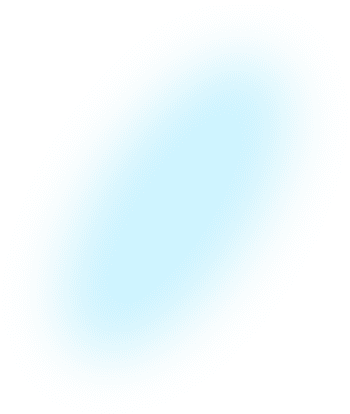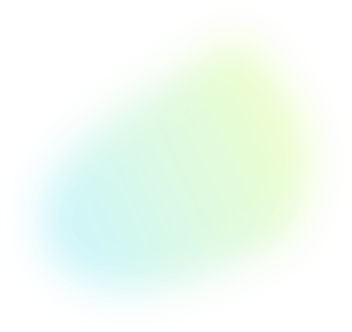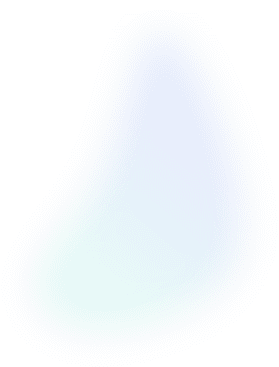加速する日本郵船グループの脱炭素に向けた取り組み
世界中で脱炭素化の気運が高まる中、海事産業においてもGHG削減は喫緊の課題だ。日本郵船グループはGHG削減の長期目標「2050年までのネット・ゼロエミッション達成」を掲げ、さまざまな取り組みを進めている。その一つである世界初の国産エンジンを搭載したアンモニア燃料アンモニア輸送船開発(以下、本プロジェクト)が、着々と進行している。
船舶における現在の主燃料である重油は、使用する際に大量のCO₂を排出する。GHG削減の目標を達成するためには、代替燃料の活用が不可欠だ。そこで脱炭素化を一気に加速させる新燃料として、燃焼してもCO₂を排出しないアンモニアに白羽の矢が立てられた。
だが本プロジェクト開始当時、アンモニアを舶用燃料として利用することは世界でも前例がなく、アンモニア燃料船の建造は未知への挑戦であった。

海運のリーディングカンパニーとして社会課題の解決に挑戦する姿勢
日本郵船グループが本プロジェクトに取り組む理由について、営業・プロジェクト管理を担当する森林は次のように語る。「少し前までは、アンモニアが燃料になるとは誰も想像していなかったと思います。しかし、海事産業の脱炭素化を加速させるには、アンモニアが最も実現可能性の高い選択肢の一つだという認識が広がりつつあります。当社は岩崎彌太郎の時代から、利益のみを追求するのではなく事業を通じて社会課題を解決することで世の中に貢献することを重視してきました。そのような会社だからこそ、他社に先駆けて次世代燃料の開発プロジェクトに踏み出せたのだと思います。」
森林は2022年にキャリア採用で入社した。入社後すぐにアンモニア燃料アンモニア輸送船の開発プロジェクトの担当を任され、「未知の海運分野でいきなり応用問題に挑むようなハードル」を感じることもあったが、その社会的意義の大きさを思うとプロジェクトに携わることへの高揚感の方が大きくなったという。「本プロジェクトの担当となってからは、常に船舶の専門知識をインプットする日々です。正直、今でもついていくのに精一杯ですが、挑戦を後押ししてくれる企業文化もあり、とても刺激的な毎日です。本船の開発・竣工だけをプロジェクトのゴールとせず、次にどうつなげていくか、いかに日本海事クラスターを強化し、社会全体に利益をもたらすか。また、安全性を保ちつつフェアな国際ルールの策定に貢献できるか、日々模索中です」と語る。
本プロジェクトは次世代船舶を社会実装することに加え、アンモニアバリューチェーンの構築や新たな技術開発を通じた日本の海事産業の強化、アンモニアの船舶での利用に係る国際ルール化への貢献など、より広く社会に貢献する目標を掲げている。社会に、そして国全体の利益に資する事業にするという大きな意志がここにある。

譲れない「安全と品質」
これまでに機関士として、LNG運搬船を中心に多くの船で海上勤務に従事してきた髙森は、安全性確保の観点から必要不可欠となる船員の目線で本プロジェクトに携わっている。「アンモニアには健康被害のリスクがあり、取り扱いには万全の安全対策が必須です。船員として不安がないわけではありませんが、船は船員が乗らないと走りません。しっかりと安全性を担保し、船員が安心して乗れる次世代船舶を作る。それを成し遂げるために、私がここにいます」と、自身の役割と責任について力強く語る。
アンモニアは肥料や化学原料、発電所の脱硝材などに利用されている。安全性の検討に際して、髙森はアンモニアを扱う既存事業者へ足を運び、安全対策などのヒアリングを実施。現地現物で学んだ知見を社内や開発パートナーとも共有し、安全性に関する研究開発を進める。「いかなる形であれ、運航中のアンモニア漏洩などがあっては、船員の安全が脅かされてしまいます。アンモニア燃料船の安全性を担保するため、経験豊富な機関士40人以上で設計図を見ながら、時間をかけて何度も検討を重ねました」と話す。
船舶の設計・開発を担当する造船技師の藤岡は、自らのキャリアの中で新技術の研究開発に携わりたいと考えていた。しかし本プロジェクトをいざ担当すると、その難易度の高さを痛感したという。「通常、我々のような海運会社が船を発注する際は、既に開発が完了した機器を組み合わせて、最適な船の仕様を決めていきます。しかし、今回は本船のコアとなるエンジン、そしてエンジンに付随する周辺機器類も全て新規開発となります。船舶の設計は経験工学という側面もあるのですが、モデルとなる本船仕様が存在しないため、機器構成から考える必要があり、何度も何度もコンソーシアムメンバーと検討を重ねて仕様を決定しました」と話す。
本プロジェクトは、日本郵船(株)を含む5者のコンソーシアムとして取り組んでおり、社外関係者ともコンセンサスを取りながら進める必要がある。「より良い次世代船舶の建造には、当然のことながらコストも時間もかかるため、予算やスケジュールはしっかり管理する必要があります。一方、納期やコストを意識しすぎて安全性を下げるわけにはいきません。技術面のみならず、安全性、納期、コストなど多面的に評価しながらバランス感覚を持って判断できる能力が求められます」。こう語る藤岡の言葉からも、安全と品質を追求する姿勢が伺える。
高い専門性を持ったメンバーがワンチームで挑む
2026年11月の本船竣工に向けて開発を進めているが、コンソーシアム各社が負う開発リスクへの評価・考え方は各社各様だ。開発にあたってはその調整も必要となった。
調整を担当した森林は、とにかく対話の機会を増やすことに注力したという。「皆さんその分野の専門家であり、それぞれの立場・考え方もさまざまで、私たちの提案がすぐに受け入れられることの方が少ないです。立場や考え方の違いの裏にある背景を理解しようと繰り返し対話を重ねることが大切だと考えています。より良い船にしたいという熱い想いを抱いているのは皆さんも同じです。相手の考えの本質を理解して、共創が成り立つポイントを探すべく奮闘する日々が今も続きます」と、体当たりで築く関係性を語った。またそれぞれの打ち合わせに森林、髙森、藤岡が互いに同行することも多いと言い、「自分の立場だけでは判断できない部分も、それぞれの専門分野の知見を持ち寄ることで、各社と建設的な対話ができています」と続ける。
髙森も、メンバーとの密な関係性について、「当社は高い専門性を有する各部署が単独でプロジェクトを完遂することが多いのですが、これほど社内横断の密度が濃いプロジェクトは見たことがありません。私たちは技術と営業が両輪となって取り組む利点を活かし、それぞれの立場から多様な意見を出し合うことで視野を広く持ち、ワンチームで動くことができています」と話す。
個々人の専門分野の知見とその総合力によって、プロジェクトの進行が支えられている。
日本の海事産業の未来を拓く
2023年12月、日本郵船、(株)ジャパンエンジンコーポレーション、(株)IHI原動機、日本シップヤード(株)の4社は、世界初となる国産エンジンを搭載したアンモニア燃料アンモニア輸送船の建造に関わる一連の契約を締結。2024年6月に竣工予定のアンモニア燃料タグボートのノウハウも反映させながら、2026年11月の竣工に向けて本格的な造船のステップに進んでいく。

アンモニア燃料アンモニア輸送船の竣工により日本郵船グループの脱炭素の取り組みは大きく前進する。藤岡は、「この一隻を皮切りに、アンモニア燃料船のさらなる普及が必要です。そのためにも仕様の最適化に向けた検討や調整をこれからも続けます。まずはこの一隻に集中してやり遂げる。その上で、より良い船を実現するための仕様検討・技術開発に尽力したいです」と、プロジェクトの先を見据えて、一歩一歩進み続ける覚悟を宣言した。
日本の技術で挑み、世界初となる国産エンジンを搭載したアンモニア燃料アンモニア輸送船が竣工した暁には、日本国内の海事産業のさらなる発展にもつながるだろう。森林は、「事務局としてこれからも調整を進め、最終的には日本海事クラスターがまだまだ躍進できることを世界に発信したい」と、今後の展望を力強く語った。
日本郵船グループの企業理念“Bringing value to life.”の通り、今後も持続的に新たな価値を人々へ届けるべく、アンモニア燃料船開発プロジェクトは重要な役割を担う。この前人未到の取り組みを確実な形にしていくため、プロジェクトメンバーはこれからも奮闘していく。
インタビュー 2024年1月22日